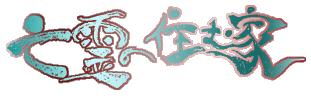
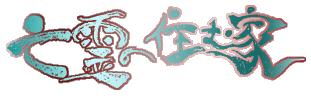
亡霊の住む家 21
『法子と雪乃 ②』
法子にとっての、屈辱の時間は続く。
法子の所有者たる男と、慈しみ育ててきた次女との狂乱の契りは、ようやく収まりを見せた。
雪乃はしどけなく全身をベッドに投げ出し、肉唇から溢れ出す精液もそのままに、荒い息をついている。
――が、まだまだ男は満足していなかったのだ。
『さあ、次はこれだ』
娘の淫液にまみれた男根が、言葉と共にむくむくとその形を変えていく。
巨大でグロテスクな形――人の物の形ではない、凶悪な――。
未知の惑星の生物のような、イボと、棘とも言うべき突起を全身に纏ったそのフォルム。
つい先日、彼女を蹂躙し、征服し、文字通りにヨガり狂わせた、あの肉棒だ。
自然に法子の喉が、ひぃっ、と鳴った。
「お願い……お願いですから、やめてください……雪乃が、雪乃が壊れてしまいます!!」
『くくく、まあ私としては雪乃でも法子でも、どちらでもいいがな。では、お前が身代わりになるか?』
「――わ、私が――」
法子が言い掛けた瞬間、
「――いいえ、そのまま私を犯してください。わたしはご主人さまの物ですもの。受け入れて、見せます……」
一瞬の逡巡を突いて、雪乃が先回りするように答えていた。
「ゆ、雪乃っ!!」
娘の台詞に驚愕の視線を向ける法子に、雪乃は挑むように応える。
「さっきも言ったでしょ、お母さんは黙って見てて。横取りなんかさせないんだから」
「雪乃……!!」
未だに金縛りが解けずに動けない彼女に、成す術は無かった。
『まずは舐めろ。流石に大きいからな、出来るだけ滑る様にしておけ』
「はい……」
起き上がり、横目で勝ち誇るような視線を法子に向けながら、雪乃は男の前に跪いた。
「すごい……逞しいです、ご主人さまの……これが、私の中に……」
娘と、男の視線が絡み合う。
『そうだ、これがお前の相手だ……しっかりと、舐めておけよ……』
「は、い……」
雪乃の舌先が、恐る恐る、男根の先端に触れる。
先端をちろちろと舐め、そのまま根元へと這わせていった。
「ん、ん……ちゅっ、ちゅ……」
舌先は次第に大胆さを増しながら、何度も何度も、先端から根元へと往復する。
ほどなく男根は、ぬらぬらと全身に雪乃の唾液を纏わせ、天を向いて屹立した。
「……雪乃ぉ……」
実の母親の力尽きたような呟きに、雪乃は答えもしない。
ただ、うっとりとした視線を巨大な肉棒に這わせ、少女とは思えない淫蕩な笑みを浮かべていた。
「……、準備、できました、ご主人さま……」
『よし……では、そこに跨って尻を上げろ』
「はい……」
雪乃は法子の胸の辺りを、尻をを向けて跨ぐ位置で四つんばいになり、腰を高く掲げた。
目の前に、雪乃の陰部が見える。
その美しいピンク色はまだ、全く穢れも無い少女に見えるのに――そこはもう、唾液と愛液と、そして精液でドロドロになっていた。
『さあ……行くぞ』
法子の目の前で、幼い秘唇に巨大な男根が突きつけられ、潜り込んでいく。
ずぶ……
「あ……」
先端が潜り込み、雪乃が漏らした微かな悦楽の声は、たちまちのうちに苦悶の叫びに変わった。
ずぶ、ずぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ずぐんっ!!
「ああぁ、あぐ、ぐ――ぁぁぁぁああああああああああああああああーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ!!!」
みちみちと肉の悲鳴を上げながらも、幼い雪乃の膣はソレを飲み込んでいく。
それは悪夢のような、信じられない光景だった。
(そんな、そんな――)
ぎちぎちと、幼い柔肉が蹂躙される。
ずぐ、ずぐ、ずぐ、ずぐ……
少女の腕ほどもある肉塊が、その身体を貫いているのだ。
「あう、あああぅ、うあああぅぅぅ……」
母親である法子には、それを現実の光景だと受け入れる事が、できなかった。
『くっくっく……流石に、物凄い締め付けだな』
ずぐ、ずぐん、ずぐん、ずぐんっ……
「うぁ、ぁ、あああぁぁ、あぐ、あうぅぅぅ、あああっ、あぅあああああああっ!!!」
掻き分け、抉り、こじ広げるように、男は動きを進めていく。
肉棒そのものも細かく蠕動し、自らの巨体の進入を援けているようだ。
そして男の腰はそのまま、強引に往復の動きを始めていた。
ぐっ、ぐぶぶっ、ぐっ、ぐぶぶっ、ぐっ……
『どうだ? イボはわざとカエシになるようにしたからな……抜く時も気持ち良いだろう?』
「ああっ……あああああっ…………」
膣壁を引きずり出されるような感触に、雪乃の身体が慄いている。
「あああ……雪乃、雪乃、雪乃……」
ぽた、ぽたた、と、愛液とも精液ともつかない雫が、法子の頬に掛かる。
法子は慄然として、その光景を見上げていた。
悟ったのだ。雪乃が――こんなにも幼い愛娘が、この巨大な肉棒を受け入れ――そして、感じている、という事を。
ずぐ、ずぐ、ずぐ、ずぐ――
「ああ、あああっ、あぐ、あああう、うう、うあああああっ……」
雪乃の苦悶の呻きの中に、法子は確かに、艶のある響きを聞き分けていた。
よく見れば、悦楽の証である愛液までもが、ぬらぬらと肉棒に纏わり始めている。
そうだ――あのイボイボが、女の理性を容易く焼き切ってしまうのだ。
膣の内側、襞の奥の奥、ギリギリまで引き伸ばされた膣壁の隅までも、抉り、引っ掻かいて――。
一方で、子宮の入り口を抉る先端も、ただ突き上げているのではない。
その、イボを無数に生やした亀頭は絶えず蠢いていて、ごりごりと子宮口をこじ開けようとする――。
そして……やがてその先端が、別の生き物のようにくねって、侵入する角度を探るのだ。
やがて的確なベクトルを掴んだ先端は、硬く、そしてしなやかに、突き、突き上げ――。
「う……わ、うわぁぁあああああああああっ!!!!」
そして、ついには子宮の中にまで突きこまれるのだ……。
覚えている――。あの、理性を直接削り取られるような、快感を。
見えていなくても容易に想像できた。子宮から直接響く、魂までもを揺さぶるような悦楽を。
法子の膣が狂おしく、欲求不満の叫びを上げ始めていた。
ずぐん、ずぐ、ずぐ、ずぐん――
「……ひ…………っ、………………は…………ぁ……」
悶え、泣き狂う雪乃。
イッている。イキながら、咽び泣いているのだ。
法子は、そんな犯されていく自分の娘の姿に、半ば魅せられていた。
(ああ……)
『ああ、もうそろそろ出すぞ、受け止めろ、雪乃……』
そして――法子は、目くるめく悦楽の最果てにあった、あの射精を思い出した。
「あ……だめ、雪乃、それだけはだめぇぇっ!!」
だが、その叫びは既に遅く、そして無力だった。
『う、おお、おおおおおおおおおおっ!!!!!』
どく、どくんっ!! ごぷ……ごぽぽ、びゅるっ、びゅるるっ……
「…………………………ひ……………………ぐ……っ…………………………!!!!!」
あっという間にその幼い膣と子宮を満たし、溢れ出た精液の奔流に、雪乃もまた絶頂を迎えた。
どっと雪乃の全身が汗を纏い、突っ張り、激しく戦慄く。
(あ、あ、あ……)
法子は茫然自失のまま、成す術も無くその光景を、脳髄に焼き付けてしまう。
射精への渇望、動けない自分への惨めさ。
湧き上がる、暗雲のようなどドス黒い感情。
「ぁ…………ぁ…………、きてる……ごしゅじんさまが、入ってきてるぅ………………」
愛娘の恍惚とした、その表情。親の自分でさえ見た事の無い、蕩け切った無防備な笑顔。
今まさに、魂までも男に侵食されていく、あの愉悦を味わっているのだと思うと、妬みの炎がチリチリと法子の脳髄を焼いた。
(私だって――私だって、雪乃の年頃に御主人様に出会えていれば……)
◇
だが――。
『今後は、法子のみを私の正式な奴隷とする』
ようやく狂乱の興奮が収まった私達に掛けられた言葉は、意外な物だった。
「な、っ、――」
絶句する雪乃を見下すように睥睨し、御主人様は言葉を継ぐ。
『今夜はな、二人を味わってその優劣をつける事にしていたのだ。そしてその答えが、これだ』
がく、がくがくがく――と娘の全身が震え始めた。顔面も蒼白だ。
『膣の具合については若さと成熟度で甲乙つけ難い。問題は、その言動の品格だ。後輩の奴隷に当たるとはいえ産みの母親に向かっての暴言の数々、目に余る』
「あ、ぁ、ぁ…………」
思わず差し伸べようとしたその手を思い留めたのは、目の前の御主人様への遠慮か、それとも心の底に燻る暗い喜びの所為なのか。自分でも分からない。
でも、確かに私は今、勝者としての、選ばれた女としての、紛れも無い歓喜を感じていた。
『それにお前も、アキラとかいう餓鬼を裏切っているではないか。あまり母親のことを言えた義理ではないだろう』
「い、いや、いやぁぁ……」
『私の奴隷に必要な素質は閨での良し悪しだけではない。その振る舞いや言動にも当然、相応の品格が要求される』
「あぁぁ、あぁ、あぁぁぁ……」
瞳の瞳孔が、きゅっと閉じる。
『先刻の雪乃の言動はそれを全く満たしていない。よって法子は合格とし、雪乃は失格とする』
「嫌、いや、いやぁぁぁぁぁぁあああああああああっ!!!!!」
掠れ声の絶叫が、寝室を満たした。
「ご主人さまっ、す、すてないで、捨てないで下さい、お願いです、す、捨てられるなんて、嫌、いやぁぁ……」
『私の決定に、逆らうのか?』
御主人様はすがりつく雪乃に意地悪な笑みを向け、そして私に目配せした。
「いやああぁぁぁっ、お、お願い、おねがいしますぅ、わた、わたし……もう、生きていけない……」
(あ……)
その視線だけで、私は御主人様の意図を理解した。
この御方は、雪乃の勝気な言動を押さえ込む為に一芝居打っているのだ。
『だが、そうだな――法子、お前に一つ権限をやろう』
「……権限、ですか?」
『そうだ。お前が望むなら、雪乃を我が奴隷のままにしておいてやってもいい』
「「――!!」」
私達は、同時に息を飲む。
『お前はいつでも雪乃を我が奴隷のリストから追放できる。その権限を以って娘を躾けろ。親として、そして性奴として――な』
「――分かりました」
呆然とした雪乃を庇うように、私は即座に答えていた。
「お、お母さん……」
「大丈夫、大丈夫だから。あなたを追い出すなんて事は決してしないわ、安心して」
半信半疑の様子の雪乃に、優しく微笑み掛ける。
「……」
娘を抱き寄せ、子供の頃のようにその髪を撫で付ける。
「一人で寂しかったのね、これらからお母さんが護ってあげるから」
「う……」
堪え切れずに、雪乃は泣き出していた。ここ数週間の緊張の糸が切れ、心の堰が一気に崩れたのだろう。
「うわぁぁ……ぁぁぁ…………」
「大丈夫、もう、大丈夫だから……」
「怖かった……怖かったよぉ……」
子供のように泣きじゃくる雪乃と、彼女をその胸に抱き締める私。それは紛れも無い、親子の美しい構図、なのだろう。
「だから、これからはお母さんの言う事を良く聞いて、ね?」
「うん……」
(御主人様、これでいいですか?)
私の伺うような視線に、御主人様は軽く頷いた。
『いいだろう。二人ともこれまでと同じように、我が性奴として尽くすのだぞ』
「――!! あ、ありがとうございます、御主人様……」
「ぁ、ありがとお、ございますぅ……」
安堵と嗚咽の入り混じった表情で、私達は抱き合ったまま跪き、頭を垂れた。
『私の命令は何よりも――家族の情よりも優先されねばならん。だが、それは肉親の絆を断てという意味ではないのだ。分かるな?』
「……」
頷きあう二人を見て、御主人様は満足げに言葉を続ける。
『そしてお前達がこの暖かい家族を失いたくないのならば――家族全員が、我が奴隷となるしかない』
「!!!」
その言葉の意味に私は驚愕し、雪乃は悔しそうにきゅっと唇を噛んだ。
『――どうだ? 私はこれから、由佳と鈴穂を奴隷に加える。それでも付いて来るか?』
「――――――」
そう言った以上、御主人様は必ずそれを実行されるだろう。
私達には止められない。捨てられる――そう考えるだけで身が竦むのだ。逆らう事など出来る訳が無い。
『付いて来るならば、今ここで誓うのだ……我が命令の全てに、無条件で従うと』
数秒の逡巡の後、私と雪乃はきっと男を見上げた。
「「従います」」
かつて愛した夫の前で、父親の前で、私達は、自らの運命を選択した。
もはや戻れない――その事実は、もう私達を苛まない。
晴れやかに、決然たる決意で、私達は互いを祝福し、微笑み合った。
◇
そして――。
「あっ、あああっ、ぅああああああっ!!!!」
「ひっ、ぐ……あぁ、あああぁぁ…………」
美しき親娘は、男に「同時に」犯されていた。
二人を向かい合わせに座らせ、胴体から生えた二本の巨大な凶根が、下から彼女達を貫いている。
「あぁ、はぁぁぁ、嬉しい、やっと、やっと……」
「うぁっ、ああぁっ、壊れ、ちゃぅ……ぅぅ……」
二人は抱き合い、互いの身体を支えながら突き上げられ、喘いでいた。
組まれた腕に閉じ込められた二人の膨らみが、窮屈そうに押し合い、形を変えている。そこに青白く異様に長い手が絡み付き、4つの乳房と乳首を巧みに弄んでいた。
胴体と腰も異様に伸び、まるで櫛の歯のように巨大な肉棒を並べて生やす――その姿は最早、人の形とは言えない。
だが、法子にはもう、何の恐怖も不安も無かった。
「ああ、やっぱり凄い、凄いのぉぉ、グリグリって、一杯、一杯ぃ……」
「あひっ、ひぃぃっ、ひぃぃぃ…………」
目の前でずっと見せつけられていた男根が、ようやく自分を満たしてくれた充足感。
人外の存在に身を委ねる「仲間」が出来た安心感。
そして、男のお陰で取り戻せた親子の絆。夫を捨てた母親失格の自分が、再び娘を取り戻せたという喜び。
それらの全てが法子の魂を揺さぶり、打ち震わせ、そして酔わせていた。
もう何度も撃ち出されている男の精液が、男の精神の欠片が、その魂の「隙」に染み込んでいく。
「あああ、幸せ、幸せ、幸せですぅぅ…………もっと、もっと突き上げて下さいぃっ!!!」
「あ、う、ぁ……あぁぁ…………」
膣壁を抉るような摩擦も、子宮を壊されそうな衝撃も、今の法子にはたまらないほどの愉悦だ。
全てを壊され、そして全てを与えられ、全てを満たされて――法子の魂はここに於いて、完全に支配された。
もう何も、怖くない。迷いも無い。躊躇も無い。
残る自分の人生の全てを、自分は彼に捧げたのだ。
素晴らしい。なんという開放感。なんという幸せ。今まで必死に守ってきた誇りや貞操が、今は酷くくだらない、つまらない物に見える。
「うあっ、ああああああっ、イク、イク、イクぅぅぅ、がっ、ひ……………………っ!!!!!」
「あ…………っ、あぁぁ…………っ、うぁ………………………………………………っ!!!!!」
これで私は満たされ、私の未来は定まった――。
最後の突き上げと、迸る精を子宮の奥に受けながら、法子は絶叫と共に悟り、そして、果てた。
◇
愉悦の叫びを上げてのたうつ法子の横で、雪乃は朦朧としたまま幾度目かの絶頂を迎えていた。
途中から、記憶が途切れ掛けている。
成熟した身体を持つ母と肩を並べるには、彼女はまだ未成熟過ぎたのだ。
絶頂のもたらした、銀色に染まった意識の中で、雪乃は遠く響くような母と男の声を聞いた。
『ふふ、こうもあっさりと失神してしまうとは、性奴としての躾が必要のようだな』
「はい、御主人様……しっかり躾けて、鍛え直します……」
――ああ。お母さんも、完全にご主人さまの奴隷になったんだ……。
漠然とそんな事を考えていると、突然その母に圧し掛かられた。
「!? おかあさ……!?」
「雪乃。折角の御主人様の御寵愛で気を失ってしまうなんて。――お仕置きよ」
猫撫で声のような、笑い声のような――雪乃が今まで聞いた事の無い声音で、母が言った。
「え、え……!?」
「もっともっと、身体を成熟させないといけないわね……大人しくしているのよ」
その言葉の意味を理解するより前に、胸から熱い感触が届いた。
ねっとりと絡みつくような、熱くてざらついた感触――。
(お、お母さんっ!?)
母が、自分の乳首を舐めている――その衝撃に、雪乃の意識は一気に覚醒した。
「やっ、やめてっ、お母さんっ!?」
法子は答えなかった。娘の狼狽にも構わずに、舌と唇、そして両手の指を駆使して雪乃の全身を愛撫していく。
(う、そ――!?)
組み伏せられて初めて分かるその実力差に、雪乃は慄然とした。
何より成熟した肉体を持つ法子が相手では、体格からして違うのだ。一度押さえ込まれてしまえば、もう逃げる事はできない。
――そして、その技巧の差。
男性経験こそ乏しいが、相手が女性の身体ならば二十年以上の付き合いだ。
幼さの残る少女を舞い上がらせる事くらい、法子にとってはそれこそ赤子の手を捻るよりも簡単だった。
「うふふ、やっぱり私の娘ね…弱い所まで私にそっくり」
「あっ、いやぁっ、イヤぁぁぁぁっ!!!」
あっという間に大きく開いた両脚の間に身体を割り込まれ、たちまちのうちに雪乃は窮地に立たされた。
耳、首筋、脇の下、乳房、うなじ、太股、臍、そして乳首――。
身動きの取れない少女の身体に、十本の指と、唇と舌が、容赦なく襲い掛かる。
「親娘ですものね……感じるところなんて全部お見通しよ?」
「ひ…………っ…………!!!」
ちゅ、ちゅ、ちゅる……ちゅく、ちゅくちゅく……
あくまで男性的な「ご主人さま」の攻めとは違う――目の前の女を責め上げ、追い詰め、堕とす事を目的とした、容赦の無い攻めだった。
自らの身体で知り尽くした女の弱点を、法子は迷うことなく突き、抉っていく。
「ここでしょ? あら……ここもかしら?」
「あ、ひ、ひぃぃぃっ、や、あ、あ、やぁぁぁっ!?」
何をされているのかも把握できずに、雪乃はただ、その快楽に翻弄される。
信じられないほど繊細で、巧みで、そして貪欲な指の動き。クリトリスを掘り起こされ、転がされ、そして捲られ、そこを舐められた。
電気ショックのような快感に、雪乃の身体は本人の意思を無視して勝手に飛び跳ね、のたうち回る。
「嫌ぁ、ご主人さま以外にイかされるなんて、嫌、いやぁぁぁっ!!!」
――レベルが違う。雪乃は戦慄と共に、思い知った。
耐えようと、身構えようとするその前に、回り込まれるようにその緊張が突き崩されてしまう。
いとも容易く、しかも的確に。常に数手先を読まれているゲームのような物だった。
「あらあら、もう限界? この調子だと何回イッちゃうか分からないわよ?」
雪乃の悲鳴に、母の猫撫で声のような言葉が重なる。
その声にはウズウズするような嗜虐的な喜びの響きがあり、雪乃を更に慄然とさせた。そして――
――ざらり。
「あ、や、やぁ、ああぁ、あ!? あはぁ、あああ、あぁぁああーーーーーーーーーーーーーーーーっ!!!!!」
必死に堪えているところを、耳への不意打ちであっさりと突き崩され、あっという間に雪乃は絶頂を迎えてしまう。
「あぁぁぁぁ…………あぅ、ぅ…………イカされちゃった……イカされちゃったよぉ……ご主人さまじゃないのにぃ……」
だが雪乃は、屈辱の絶頂に酔うことさえできなかった。脳髄を貫くような苦痛が、彼女を天国から地獄へと叩き落したのだ。
「ひぃぃ……!!!? い、痛ぁ、痛いぃぃぃぃぃっ!!!!」
「雪乃? そんな生意気な口を利いては駄目よ?」
少女の視線の先で、法子が強く強く、爪を立てて、乳首を抓っていた。
「あ。ぁ……!? い、痛い、お母さん、痛いよぉ……っ!!!」
だが娘の悲鳴を無視し、母は背筋に悪寒が走るような猫撫で声で言葉を続ける。
「あなたは私に逆らえないの。逆らったら性奴失格なのよ、分かるかしら?」
「ひぃ…………!?」
――ゾッとした。
あまりの母親の豹変振りに、雪乃の全身がガクガクと震え始める。
生まれて始めての、まるで別人のような母の表情、そして口調。
それは、雪乃がなけなしのプライドをかなぐり捨てるのに、十分過ぎる苦痛と恐怖だった。
「あぁ、あ。ご、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいぃぃ…………」
手足を押さえつけられていなければ、這い蹲って謝罪しただろう――そうとまで思わせる、必死の声音だった。
それでも法子は手を緩めず、捻り上げるように雪乃の乳首を抓り続ける。
「いやぁぁぁっ、い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛い、痛いぃぃぃぃっ!!!!」
「な、に、が、ごめんなさい、なのかしら? ちゃんと言わないと許してあげないわよ?」
事ここに来て、とうとう雪乃のプライドは根底から砕け、崩れ落ちた。
童女のように泣き喚きながら、ひっくひっくと途切れ途切れに言葉を紡ぐ。
「生意気言って、ごめんなさいぃ、逆らってごめんなさい、ひっく、もう、言いません、うぅぅぅ……ぅぅぅ……」
途端に、法子の表情が晴れ渡った。これまでの仮面のような笑顔が嘘のように、慈愛に満ちた微笑みで雪乃の頬を撫でる。
「そう、それでいいの。よく言えたわね、雪乃。ご褒美よ」
同時に、指と舌の攻めも一転した。
さっきまできつく抓っていた乳首を優しく労わるように舐め始め、白い指が肉襞とクリトリスに纏わり付き、ぬるぬると蠢き始める。
たちまちのうちに、雪乃の身体は反応し始めた。
「あ、あ、あ!!! ひぁ、あぁぁ、あ!? ひゃぁんっ、あああっ!!!」
甘露の直後に襲ってきた苦痛、そしてまた訪れた甘露――。少女はその落差の連続に混乱し、あっさりと陥落していく。
元より、抵抗する体力など全く残っていなかった。
何十回目の絶頂になるのか――そう、他人事のように、ぼうっと考える事しかできない。
「あ、ぁ、ぁ…………は、ぐぅ…………っ!!!!! はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ…………」
それが歓喜の涙なのか、それとも悔恨か、恥辱なのか――もう、雪乃自身にも分からない。
でも、雪乃はその後ずっと、イキ果てて気絶するまで、涙が止まらなかった。
真っ白な大波に翻弄されるように、ただただ喘ぎ、のた打ち回り、泣き咽び、そして酔い痴れた。
ライバル視していた母に、全てを曝け出してしまったマゾヒスティックな悦び。
戦っていた相手に腹を見せる犬のような、徹底的な降伏と媚びを見せる、その開放感。
初めて抱いた母親への恐怖と、同時に混在する母への赤子のような甘え。
そして、それら全てを包み込む、自分の所有者であり守護者でもある男への、安心感。
粉々に砕かれたプライド――自我の在るべき場所に、それらが陶然と流れ込んでいく。
(あ、あ、あ…………)
全てが混ざり合い、溶け合って、それが新たな「雪乃」を象っていく。
――新しい雪乃に、なっていく。
◇
『上出来だ。よくやったな、法子』
「はい……」
ひくひくと絶頂の余韻に身を震わせる愛娘を前に、法子はうっとりと微笑みながら頷いた。
勝利の余韻が消えても、今の彼女に自己嫌悪は無い。
雪乃はもはや自分の娘であると同時に、躾を施すべき部下奴隷なのだ。
今の法子を満たしているのは、親としての愛情と――使命を果たした達成感だった。
『それでは褒美をくれてやろう。四つん這いになってこちらに尻を突き出せ』
「は、はい!!!」
全ては御主人様の思い通りだったのだろう。
雪乃の暴走も、私の嫉妬も。そしてそれらを巧みに利用され、その結果、二人が完全に彼の物になってしまった事も。
でも、それでいい。
雪乃を従わせた時、ドス黒い悦びがゾクゾクと背骨を這い上がった。
隠されていた、私の本質。
支配する者。恐怖を与え、隷属を強要する、その高みから見下ろすような悦び。
御主人様は、私の中に眠るその欲求までをも見抜き、糸で私を操るように私と、そして雪乃を堕落させたのだ。
でももう、悔しさは無い。
これだけ巧みに自在に人の心を読み、操って見せる彼に、大いなる畏敬と、頼もしさを感じるだけだ。
「は……あ、っ!!!」
その身体を開き、再び男の侵入を受け入れながら、法子は蕩けるような笑顔を浮かべていた。
◇
そして、変わらぬようで新たな日常が始まる。
「……あら、眠いの、雪乃?」
「……うん、疲れが、抜けなくて……」
「仕方ないわねえ、学校に連絡するから、今日は休みなさい」
「は〜い……ありがと、お母さん……」
新たなる支配者への恭順と服従――その屈辱を受け入れ、代わりに雪乃は母親という絶対的な守護者を得た。
主人に加えて、新たに強力な精神的支柱を持った雪乃の自我は補強され、その安心感という名の快楽に酔い、満たされ、依存していく。
砕かれたプライドの残滓が僅かに疼いたが、それも些細なことだ。
人ならざる者にたった一人で付き従う――心の奥底に溜め込んでいたその孤独は今、癒され、不安は満たされた。
同時に彼への無条件の盲従と同じ、思考放棄にも似た絶対的な服従をすべき相手の中に、母が加わった事になる。
「うふふ……」
一方で法子も、盲従と言っても過言ではない雪乃の態度にこの上ない優越感と満足感を覚えていた。
幼子の頃のように、無防備な笑顔を向けてくる愛娘。可愛くない筈がない。愛しくない筈がなかった。
女としてのプライドは満たされ、母としての庇護欲が掻き立てられる。
それは、完全に利害の一致した奴隷達の上下関係であり、同時にこの上ない愛に結ばれた親娘の関係だった。
そして、この関係こそが男の目論んだ計画の一端――この家庭に打ち込んだ楔の、最初の一つだった。
(仲直り、したみたいだね……)
(うん、昨日の夜はどうなるかと思ったけど……)
昨日とは打って変わって仲睦まじい二人の様子に、由佳も鈴穂もほっとした視線を送る。
その裏側に潜む、邪な意思にも気付かずに――それが、自分達を窮地に陥れる一手だという事にも、気付かずに。
亡霊の住む家 22 に続く