![]()
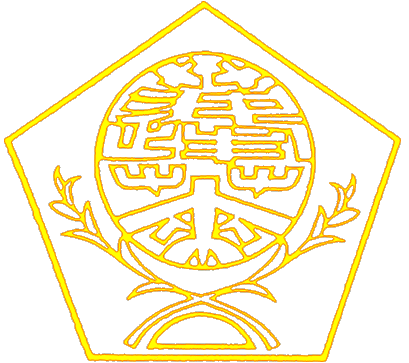
![]()
其の1
光が声をかけた時意識の無かった女生徒
達も体中をまさぐられても気が付かないはずもなくあちらこちらで羞恥にうち奮える声が聞こえて来る、
ここに集められた女生徒の内約半数がお料理研に何かしら籍を置く者だったとはいえ驚くほどにバラエティーに富んだ顔ぶれだったといえる。
光と同じ組で料理をしていた未来マリア(ミキ・−−−)は新体操部の1年生で胸の厚みに少しばかり寂しいものを感じるものの本人の談によれば……
『これから揉まれて大きくするのよ」
……との事で、今、は見知らぬ男にゆっくりと揉みし抱かれている所であった。
「やっ やめてぇください……」
といつもの言葉を忘れて見知らぬ男に先程から繰り返し繰り返し動かぬ頭を下げていた。
そして男の言葉も決まって
「モット強く揉んだ方が大きくなる、サービスだから気にする事ないぜ」
というものだった。
身体が動かない事がかえって刺激を強くするらしく男が胸を強く握る度に痛いのようなむず痒いようなマリアには既に理解不能だった。ただマリアの祖母譲りの白い透けるような肌が先程からピンクに染まり男の目を楽しませていた。
「ひやぁ だめでる、出ちゃうっくぅふはぁん」
シャァァァァァ
「けっきったねえ」
マリアは何が自分の身体で起きたのか知らなかった、生温かい感覚が股間をつたいそこに黄金水の水たまりを創っていた。
「ほほう、そんなに気持ち良かったのかい でも後始末くらいは自分でしろよ」
男は、マリアの肩のところできれいに切りそろえられた朱い髪を無造作に掴むと水たまりに顔を着けさせて
「なめ取れ!」
「キャッ」
グリグリと顔を水たまりの中に押し付け
「出来るだろ?」
ともう一方の空いている手の指を股間の女陰へと這わせる。
「ふぁい!」
すると男の手の下で、ピチャピチャという音が聞こえ出した。がっ この時、男は他の事を考えていた。
「処女かいこの女郎」
「お〜い コアラ〜」
男はエプロンにコアラの刺繍をしている男を呼ぶとマリアから取り上げた生徒証を見せて
「マリアなら処女受胎が基本だろ」
一瞬コアラ男は驚いたような顔をし……
そして笑った。
「そうだね、僕が生物部で狂的化学部でその上研究室に籍を置いているってよく知っていたね」
それに男は無言で答えて
「ヨオシとびっきりの子供を産ませてあげる」
コアラ男は自分の鞄を取りに踵を返すと飛び出して行った。
「面白いお皿になれるぞマリア、1日もすればお前は今は何処にも存在しないような生き物の母になれるんだぜ」
男の指が、ひっきり無しに与える快楽のが意識を奪う小水とは違う粘液質の液体が、女陰から溢れ、くびれたウエストから小さな胸の谷間と渡り、喉から顎へと、そして糸を引きながら水たまりを作っているもう一つの液体の中へと伝う、そしてそれをマリアはまぜこぜにして胃の中へと納めて行った。
自分の不幸な『未来』が会ったばかりの見ず知らずの男達の間で決められた事も知らず>に。
「アハッ」
其の2
おたまを落とした女生徒、西神田伊代(ニシカンダ・イヨ)はマリアよりはましな状況かもしれない、しかしこの生活委員会所属の1年生にとってはおそらくマリアの方が幸せだったと言うだろう。
彼女のおなかは既に妊婦のようにふくらみ、分娩室でつわりに耐える女性のように全身から脂汗を流していた。
「くっ……」
口をパクパクさせて鯉が餌を貰う時のようにして伊代は耐えていた。最後の一瞬が来る事を信じて。
「ほうらどうだいだいぶ綺麗になっただろう」
アライグマの刺繍が入ったエプロンを茶色く汚した小柄の男は嬉しそうに赤紫色にすぼまった器官を見つめた。
「もうダメェーー」
ブヴァッ ヴリビリヴァリバラーー
何かが裂けるような音とともに限界を超えて高められた腹圧によってそのダムは6度目の決壊を起こした。
「あぁぁぁぁぁっっっっっ いいいいいいやああぁぁぁぁ」
そして今日六度目の消えいりそうな悲鳴が伊代の口から漏れた。
何リットルの液体が吐き出されたのは解らないがようやく彼女の菊門は閉じたのだ、アライグマ君はその液体を愛おしそうにボウルからパチャパチャと自分にかけた。
「いい香りだそして……」
無造作に伊代のおなかに手をのせるとグイッと体重をかけて
「この最後の一滴までが最高さ」
ビュルッと吹き出した何かしら滓のような物の浮いた液体をビーカーに入れて透かして見せる。
「おわりね他は何でも良いわだからお尻に何か入れるのはもうやめて……」
伊代の言葉を聞く耳も持たずにビーカーの中を口に含むと男は覆いかぶさって来る。
伊代はもう逃げなかったし、気力は訪うに果てていた。口移しで自分の排泄した物を飲まされるのも六回目だった。
するすると喉を流れて行く液体の中の浮遊物が時折喉に掛かるがそれももうなれていた。
「旨いだろう」
「は………はい……」
「そうかそうか おいしいか」
男はそう聞くと天使のような満面の笑みを浮かべる。
「じゃあもう一回、浣腸しようか!」
「そっ」
ギラリッ
鬼に変わった。
「は、はい もう一度お願いします」
「いい娘だねぇ」
そう言って男は調理室に備えつけの蛇口に取りつけた語句の管に男根を模したディルドゥを付け伊代の股間へと廻りこんで行く。
「これで最後にしてくれますね、お願いです、これで……」
カサカサする唇を引きつらせて伊代は哀願するしか無かった。
「わかってるって、一度言えばわかるよ」
「本当ですね…… 本当に」
「しつこいよ」
「ひっ」
一瞬鋭い目つきになった男はすぐ笑顔になると手で男根をしごいて見せると尻の穴に近付けて行った。先が肛門に触れる所で止めると、
「さあ、ひとこと言わなきゃ」
今までずっとこの男は伊代に変態的なおねだりをさせているのだった、これ迄の六
回ともそしてこの七回目も、
「さあ!」
「い、伊代に…… 浣腸して下さい」
ぼやけた意識で自分の排泄物を口に入れられる事よりも自分でおねだりする事の方が伊代には恥ずかしかった。
だが…
「伊代の尻の穴にだろ」
死ぬ想いで口にした言葉もこの男にはまだ不満であるらしく一度でOKが出た事は無かった。
「伊代のし…… 尻の あ、穴に浣腸をして下さい……うっ」
「よく言った、お願いされちゃったからいっぱいしてあげるよ」
喜色満面とはこの事であろう男は何度も排泄を繰り返した一点に力を加えてディルドゥを静めて行く。
「グプッ」
するりと潜り込んだディルドゥを深々通し込むとその周辺をなめ刺激を与えながら、蛇口をひねって行く。
「きひぃぃぃぃぃ、 そ、 そんなはぁ早いで、ですぐっっぷ」
ゴゴゴゴとおなかの中で水が渦を巻いていた。
「大丈夫だよ、グリセリンみたいに刺激が強過ぎるという事は無いから」
耳鳴りのような言葉が伊代の回りにあった。
「パーティーが終わったら君を貰い受けてあげるよ、気にいちゃったしね」
そう言ってアライグマ君は伊代の生徒証をかざしながら蛇口を更にひねった。
「グハッ」
伊代は何がかざされたのか知らぬままに気を失っいがっくりと首を落とした。
「良かった君もそうなんだね伊代ちゃん」
伊代はカクリとうなずいた。セミロングの黒髪に隠れて顔は男からは見えなかった。
其の3
光の後ろで芋の皮むきをしていた蘭蘭(アララギ・ラン)は既に男性経験があった事がこの場合マイナスに働いたのだろう
「もうだめです、痛いぐぅ」
大きく割り裂かれた両足を固定してその中央で息ずくいまだ使い込まれていない女
性器をラッコの刺繍が入ったエプロンをした色黒の男が左右に寛げて行く。
中国武術で修練えた軟らかい体を無理矢理くの字に曲げられて、蘭の最も隠しておきたい部分が上を向いて男の目の真下に来ている、そしてピンクの襞を丹念に広げてはクリップで
「ぎゃ」
挟んで行く。
「痛いぃ痛いぃぃぃ」
クリップをひもで腰の後ろ側を通し、もう一方の襞に
「ひぎゃぅ」
挟んで止める。
「やめて! やめてぇ」
泣き叫ぶ蘭の秘部に男は語りかける。
「大丈夫だよここは子供が出て来る場所なんだから経験あるみたいだし、経験するっ
て事は子供を創ろうとしたって事でしょ」
褐色の肌のスポーツマンに見えるこの男の手捌きはまるで医者のそれと同じであった。
「ほいこれでっと」
プシャァァァァァァ
手際よく膀胱迄通されたカテーテルが小水を体外に勢いよく吐き出して行く。
「うぶっうぶっ……」
管から吐き出されて行く液体は容赦なく蘭の顔を洗って行く。
「飲んじゃっても大丈夫だよ飲尿療法なんて流行ってるでしょ」
男は膀胱を空にすると今度は注射器のような物を取り出してカテーテルの先に付けて紅い液体を体内に注入して行く。
「ヒイィ 熱い熱いよおぉ」
蘭は身体を内側から焼かれるような感覚に震え上がった。
「ただのワインだよ後ろの方にはビールを入れるからもっときついかな」
「うそ……」
膀胱が破裂しそうな程ワインを入れるとカテーテルに栓をして男は次の準備にかかった。
「うぷう」
膀胱から尿が体内に戻るって話は本当だったんだなぁなどと朦朧としてきた意識で蘭は考えていた。早い話膀胱に入れられたワインのせいで蘭は酔っ払っていた。
「た、助けてぇ、」
という事である。
「蘭お前はパーティー会場では最も美しい酒樽になるんだよ
そしてこんな事も出来なきゃいけないんだ」
男は肛門に生ビールを入れる前に浣腸をするそして、ふくらんだズボンのジッパーを降ろすと肌よりも更に黒い肉の凶器を取り出すと蘭の唇に擦り付けて行く。
「くわえな」
其の4
光の隣の組にいた鳳縁(オオトリ・ユカリ)は珍しい2年生の内の一人だった。
そして演劇部に籍を置き普段から宝塚よろしく男役を受け持っている彼女はスレンダーな身体が魅力的だった。
「ごめんごめんこれからちょっと他の子のところに行かなくちゃいけなくなっちゃてさ〜」
コアラ男はなに気にそう言うと縁の身体を上に立てにと弄び始めた。
「くぅ、この様なばかげた事はさっさとやめるんだ」
他の子に比べて痛めつけられ方も嬲られ方も今でも全然という縁だからこその台詞であった。
「そうだよねぇ〜」
軽く受け流すコアラにはまるで響かない。それどころか縁の身体に色々な電極をし掛けていく。
「ふざけているのではない」
ちょっと声を荒げる。
「ふざけてなんかいないさぁ」
「何をしているんだ」
よくぞ聞いてくれましたとばかりにコアラは立ち上がり説明を開始する。
「実はあなたの身体にはひとつだけどうしても許容し切れない欠点があるんだ」
「欠点?」
縁が話に乗ってきたのが嬉しいらしく得意になって更に続ける。
「そう欠点 何処だかわかりますか」
まるで教師にでもなったようだ。
「わからないよ」
縁はそうは思って無いらしい。
「わかってるくせに」
でもコアラは続ける。
「わからないよ!」
今度は大声になった、そんな事はどうでもいいのだ、彼女にとっては今この瞬間でもみんなの解放の方が大事な事態なのだから
「仕方がないな〜教えてあげるよ、それは な、この小さな胸さ」
恥ずかしかった、それは大きく無い事は知っているし悩んだ事もある、でも男役によってこの傷を今まで隠してきたのにこんな何処の馬の骨とも知れない怪しい男の指摘されるなんて。
「うるさ〜い」
「恥かしがる事なんてありません、これから僕が大きくしてあげますから」
「うそ」
その縁の言葉は喜びなのか何なのか彼女自身にも理解は出来なかったしかしこの後すぐ彼女は理解するこの男はとんでもない奴で自分が悪魔に捧げられた生贄である事を……
「これをこうして注射するだけでいいんだ〜しばらく待っててね」
そう言って両の乳房の先にさっさと注射を数回打ってコアラは何処かへ行ってしまった。
「何処に行くのよ」
意識が朦朧とし身体の股間やらに取りつけられた電極が微弱な電気を流すと彼女は眠りの中へ落ちていった…
ぴちゃ
「何」
次に気が付いた時縁は何かの液体で頬を濡らしそのおかげで意識を取り戻した。
「あの男何処へ…… !」
どの位気を失っていたかとかそんな事はすぐにどうでもよくなった身体を起こそうとした時いつもと明かに違う重みが胸に付いていた、ひとつずつが縁の頭の三倍はありそうな乳房がその先から母乳を滴らせていたからだ。
「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁああああ」
其の5
この部屋のすぐ傍にある教員準備室に胡桃沢宝(クルミザワ・タカラ)がいた。
「ほうら、先生見えるか〜」
そう宝は今年大学を卒業したばかりの教師であった。
調理室がちゃんと覗けるようになっているこの部屋から宝は今繰り広げられている情景に茫然としていた。
「返事をしてくれよ〜先生」
エリマキトカゲのエプロンをした男は一年生よりも小柄で華奢に見える宝の背後から近寄って耳元でささやく。
「よっく見えるだろう、なあ 先生」
宝の身体は瞬間的に動き出した。振り向いてエリマキトカゲ君に言うのだ。
「早くやめさせなきゃ、こんなにひどい事なんで黙ったみてるの甲斐君!」
エリマキトカゲ君こと甲斐は、内心では宝に名乗ってこの集まりの教員を頼んだ事に後悔しながらも、表面的には薄笑いを浮かべているだけだった。
「見えてるんでしょ先生」
「見えているわ、だから早く何とかしなくちゃって」
宝は少しばかり焦っていた自分の教え子が男達の毒牙に掛かって悲鳴を上げているのだから、そして自分の置かれた状況を理解していなかった。
「でも解って無いみたいですね、先生」
ひゅん!
風が鳴った……
はらり……
宝のブラウスが裂けた。甲斐の手の中には小型のナイフが握られていた。
「か、甲斐君……」
ゆっくりと近寄って来る甲斐に気圧されながら少しだけ後づさってたからは調理室を覗くミラーの所で追いつめられて止まった。
「やめなさい甲斐君」
目の前に立たれると甲斐の頭は宝のそれよりも二つ分ほど上にあり見上げなければ甲斐の表情が見えなかった。
「先生……」
「な、なあに……」
甲斐は自然の流れであるかのようにナイフをタイトスカートのベルトに差し込んでそのまま下へ切り開いた、宝の足下でスカートが輪になって落ちた。
「あんたはもう帰れないんだよ」
ミラーに宝の身体を押し付けて唇を重ねる。
「ぷふぅ、どうだい先生、生徒のキスの味は? 身体小さいくせに出るとは出てんねえ」
甲斐の右腕はブラウスの下のブラをずらし、その下で官能では無く恐怖によって震え縮こまっている胸を、コリコリと揉みしだいていた。
「怯えてるのかい先生、しょうがねえなあ」
宝の身体を軽がると持ち上げると傍の机の上に載せ裂いたブラウスで両腕を縛るとストッキングを足首でひねって行動の自由を奪い取ってしまった。
「やっ…… やめ なっ なさい…… 甲斐君、な、何をする気なの」
こんな状況でも教師らしく必死に宝は振舞おうとした、だがその様がさも可笑しそうに笑いをこらえながら甲斐は冷蔵庫の中からアイスキャンディーを取り出すとそれをなめながら近づいて来る。
「リラックスさせてやるよ先生」
そう言うと無造作に動きの取れない宝の足を持ち上げて二つ折りにし色気の少ないパンティーをずらし最後の布に隠されていた中央の軟肉の中へとアイスキャンディーを突入れる。
「ひぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ! いやぁぁあぁぁぁぁぁぁっぁぁ!」
「おや?」
抵抗を感じた甲斐はアイスキャンディーを持つ手に更に力を込めた。
「だぁぁぁぁぁめえぇぇぇぇぇぇっぃっくはうぐっくあ……」
ぷちっ……
もう甲斐には解っていた、今自分のした事、今目の前の教師の身体に起こった事が
。
「先生、そうだったんですか」
ズブッ
ズブブッ
ズブブブッ
「いやぁ
いやあぁ
いやああぁぁ
許してぇぇぇぇぇぇぇぇぇ」
おもむろに、手に持ったアイスキャンディーを前後に激しく抽送する。
「痛い、痛い、痛い、やめてぇぇっぇ」
引き抜かれたアイスキャンディーは破瓜の処女血に染められて真っ赤だった。
「処女だったんですね、先生」
血に染められたそれを宝の眼前で見せびらかすものの宝はただ悲しく声を殺して啜り泣くだけであった。
「ひっ」
ズブッ
突如再びそれは差し入れられた。
気が付くと両手いっぱいにアイスキャンディーを抱えた甲斐が宝の股間の前に跪いていた。
「そのままでいいですよ先生」
次々にアイスキャンディーを血の色に染めて行く。
「ひいっ、ひぃぃぃぃっ、いやぁぁ、やめて、止めて、痛いよぉぉっぉ!」
やはり甲斐は泣き叫ぶ宝を気にも留めず全てのアイスキャンディーを赤く染めた、その頃には宝の秘部は手で触れても冷たく感じるほどに冷えきっていた。
「さ……寒い…」
身体が芯から凍えているようだった、机の上で横になった身体がガタガタと震えてあそこだけがひりひりと痛んだ。
「なに震えてるんだよ、先生」
無造作にそして容赦なく宝の濡れていないあそこへと指を這わせる。
「もうやめて、抱くなら普通にして……」
凍え切って弾力を無くした秘部は未だに血を流し続け感覚だけが遠のいている、そこへ更に甲斐はロックアイスの固まりをねじ込み始めた。
「いやあ、どうして、なんでぇ、やめてぇぇぇぇぇぇぇぇぇ」
めりっ
重い手応えの後、するんっと氷の固まりは子宮へと落ちて行った。
こつん
「ひいぃ」
こつん
「ひあぁぁ」
ゴリッ
「あがぁ」
瞬く間に子宮とそこへ通づる道は氷でいっぱいになった。
「ど、どうして…… こんなぁ」
まるで愛液を垂れ流しているかの様に股間が濡そぼり微かに血の色で染まった水がたらたらと内股をつたい落ちて行く。
ギュウゥゥゴロゴロ
「あっ」
宝の腸が冷えた結果として鳴った。
「おトイレですかはしたない、栓でもして差し上げますよ先生」
甲斐は肛門にも氷の固まりを押し付けて行く。
「先生はとあるパーティーの席上でお酒を飲む人たちの為にその身体で氷を蓄えておくんですよ」
「嘘…… くぅ はぁぁ だ ダメェ」
プシャァァァァァァァァァ!
冷たい小水が甲斐をぬらす。
「まあ、溶けて来るでしょうからその時はそのへんにいるお客の方に先生がおねだりして氷を入れてもらうんですよ、いいですね!」
ビクッ
「でも、人の身体はそんなことが出来るようには成って無いわ普通に考えればわかるでしょ」
満面の笑みで宝の顔に答えながら尻の穴へ氷を入れ続けて行く甲斐はまるで死刑執行を言い渡すかのように……
「アイスキャンディーなんかで処女を散らしちゃった先生が普通なんて言葉使うのは可笑しいですね」
ブバッ
ブビビビビビビビビッ
冷えきった腹部に溶けた氷がまるで浣腸をしたかのような効果をもたらし限界を越えた宝の肛門は一気に茶色い排泄物を体外へと吐き出して行く。
「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁああっぁぁぁぁはっぁぁぁぁぁぁ」
狭い準備室に宝の悲鳴が響きわたる。
ブラウスの切れ端とパンストが茶色く染められ。
「はぁぁぁっ」
それらに拘束された宝の身体はビクンッビクンッと昇り詰め。
「あっぁぁ」
ついに蜜壺が淫液をドロリとしたたらせる。
「あっ、あっ、あっ、くぅ」
淫液に流されて、コトリ、コトリと氷が
「ふっく…… はぁ あ」
机の上に次から次へと落ちて。
「あぁぁぁんんんっんくぅぅ」
宝自身は既に前後不覚の状態のなかで。
「へん、へんへん、へんよぉぉぉぉ」
うごめく氷に翻弄されて更なる絶頂へと突き上げられて行く。
「はあ はあ はあ あは あははは」
甲斐は冷蔵庫の前で次の氷を取り出しながらそのその様子をまじまじと見つめていた。
「先生、出してしまったらまた入れますからね」
近づいて来る甲斐の前で宝は自分で股を開いて行く。
「いやって言わせてくれないんでしょ、甲斐君」
ゆっくりとそして優しく甲斐はロックアイスを宝の中へと納めて行く。
「ねえ、甲斐君? パーティーが終わったらわたしはどうなるの」
「そうですね、僕の部屋で飼ってあげますよ、先生」
「そう ありがと」
冷蔵庫の傍においてあるパソコンのモニター上で蓬莱学園教員リストの欄の『胡桃沢宝」の項目の上でカーソルが止まっていた。
いったん抹消しようとした甲斐だったが
「授業中に嬲り痛ぶるのもいいか」
などと考え直していた。