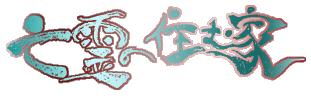
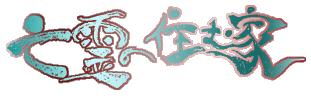
亡霊の住む家 13
『母・法子 ③』
 |
「はぅ……っ!!」 突然、掃除をしていた法子の身体に、衝撃が走った。 「……!?」 あまりの衝撃の強さと唐突さに、法子は堪らずにその場にしゃがみ込んでしまう。 突然耳元に息を吹きかけられるような、ゾクっとした悪寒が数十倍の強さで押し寄せたような……そんな衝撃だった。 足元では放り出されたままの掃除機がうるさくがなり続けている。しかし、今の法子にはそれを気にする余裕すらなかった。 「かは……ぁ、く……く……」 身体中がカッと燃え上がる。喉の渇きと快感への衝動が、凶暴に法子の身体の中で暴れまわっていた。 (──私、欲情してる!?) 気の遠くなりそうな衝動の中で、法子は空ろに考える。 ──そう、それは欲情だった。いきなりセックスの真っ最中に放り込まれたように、身体中にに火がついてしまっているのだ。 三人の娘を産んでなお、女の盛りの真っ最中にある法子の身体は、凶暴なまでの渇望と疼きを法子の中心で爆発させていた。 (な……に? 何なの!?) 法子は自分の身体を抱きしめるように両手を封じ、法子は必死にその衝動と戦わなければならなかった。 今居るリビングは、低い塀の外から見える造りになっている。万が一通行人にこんなところを見られたら……。法子は必死に身体の訴える疼きと戦いながら、障子のある和室へと這った。 (あと……少、し……) 「ふ、ぅ……うぅ……」 和室に辿り着くのがやっとだった。そのまま、畳にばたりと仰向けに倒れ込む。 |
|
そこで、法子の欲求はとうとう限界を越えた。もう、指が服の中の乳房へと動くのを止める事が出来ない。 「ああ……!!」 疲れの溜まった身体に染み渡るように、快感が走る。 自分の身体を一番良く知っているのは、自分自身の指だ。長い年月とともに指は自分の身体のポイントを知り尽くし、また身体の方もその指の愛撫に慣れてしまっていた。 手は素早くブラジャーのフロントホックを外し、乳首を直接弄りはじめる。 「かはぁ……っ!!!」 法子の口から、獣のような叫び声が洩れた。繊細な神経を刺激され、法子の乳首はむくむくと隆起し、ジンジンするほどの快感を法子に叩きつける。もう、口から洩れる喘ぎ声を押さえる事も出来なかった。 「あ・ああ、うふぅ、うぅ、ふううぅ……」 両手の指は慣れた手付きで乳首をつまみ、転がし、押しつぶして玩ぶ。乳首はその愛撫に、硬く、勃起して応えた。 ケモノのような喘ぎ声は、既に家屋の外にまで聞こえてしまうかのようにとめどなく溢れ出ていた。 上に羽織っていたカーディガンは自然に脱げ落ち、ワイシャツはボタンが半分ちぎれ飛んで乱暴に開かれていく。 腰が抜けたのか、脚はあぐらをかくようにしどけなく開かれていた。捲れ上がったスカートから垣間見える白いパンティには、既にうっすらと縦線状のシミが浮き出してきている。 (何で? なん……で……!?) いつもの自慰とはケタ違いの快感。法子の戸惑いは恐慌の域に達しつつあった。 「……!?」 どこか、遠くに嘲笑う声が聞こえた気がした。 ◇ |
 |
法子の理性は、早くも薄れ始めていた。
飢えていた身体は、今まで味わった事もない快感に泣き叫ばんばかりに反応している。
法子の最後の抵抗──それは、下半身へと伸ばされようとしている自らの手を止めようとする、絶望的な抵抗だった。
胸の愛撫を続けている左手の指が、乳首に震えるような刺激を与える度に、宙に浮いたままの右手はじり、じりと下がっていく。
法子は恐怖と絶望と、渇望が入り混じった表情で自らのもののはずの右手を見つめた。
だが、「それ」は既に自分の支配を離れ、まるで別の意識を持った生き物のように動こうとしている。──どろどろの底なし沼の中でもがくようなものだった。
「やめるのよ……これ以上は……」
 |
法子は必死に自分に言い聞かせようとする。が、胸を焦がさんばかりの渇望はいや増すばかりだった。 既に胸への愛撫は乱暴なまでに強くなっていた。引き千切らんばかりに乳首をひねり上げ、すり潰すように乳房全体を揉みしだく。そして時折羽根のような優しさで性感帯を撫で、そのまま乳首へと撫で上げる。 「こ……んな、はした……な……い……」 法子の抵抗は段々と空虚になりつつあった。ただただ快感に耐え、右手が秘部へと達しようとするのを留めようとする……。 だが、邪悪な意思はその法子の油断をついた。 再び法子の性感帯を愛撫するかのように法子の脇腹を撫で回していた左手が、いきなり右手の代りに法子の股間に突き進んだのだ。 「え!? ……あ!!」 法子が気付いた時にはもう遅い。法子が左手に力を入れようとするよりも早く、指先がパンティの中へと滑り込み、濡れた秘裂へと届いていた。 「ひいいぃぃぃ…………っ!!」 法子は今まで、秘部への刺激を意識して気の遠くなるような時間を耐えていた。 それは裏を返せば、女芯への愛撫を焦らしに焦らされていたような状態に追い込まれていたとも言える。 彼の催眠術のような言葉の効果がこれに上乗せされての快感は、法子の理性をあっさりと吹き飛ばしてしまった。 ずぷ、と意外なほどあっさりと指が女芯へと滑り込み、そのままGスポットを直撃する。 法子の一番の弱点であるそこをぐりぐりぐりと擦られ、法子の視界は真っ白になった。 |
「い、いゃああああああああああああーーーーーーーーーーーーーーーっ!!!!」
押し寄せる快感に屈服して、絶頂する法子。
だが、薄れ行く意識の中で、法子は『まだまだ、満足するのは早い……』という声を、
どこか遠くに、聞いた。
◇
法子の身体は絶頂を迎え、びくんびくんと喜悦に震えている。
だが、これだけではなかった。
震えて力の入らない法子の両脚を、何かがぐい、と持ち上げたのだ。
姿は見えない。だが、脚は誰かに持ち上げられるように、天井へ向けて伸ばされていく。
「……だ、れ……?」
法子のぼやけた視界には何も映らない。
法子の問いかけに応えず、「何か」はぐい、と法子の下着に手を掛けた。
「!?」
急いで止めようとしたが、先刻の絶頂で力が抜けきったのか、手はゆっくりとしか動かない。そのまま一気に下着は下ろされ、ひんやりした和室の空気に法子の秘部が晒された。
「い、いや……」
ぐい、と両脚を広げられ、消え入りそうな声で悲鳴をあげたが、もちろん何の応えもない。
「や、やめ、て……ひいぃ!」
いきなり、ざらりとした感触が法子の身体を突き抜けた。
「あ……な、何!? ……ひぃぃ!!」
ざらり、ざらりと生暖かい湿ったものが──
──舌!? 舐められてる!?
「い……いや、嫌、嫌ァァっ!!!」
自分が何をされているのかを悟り、法子の中に激しい羞恥が駆け抜けた。
見知らぬ何者かに「女」を舐められる──法子は狂ったように相手を振り解こうとするが、両脚をがっしりと抱え込まれているようで、ぴくりとも動かない。
「や、やめて、やめて、やめてぇぇ、ひいいっ!!!」
ざらり、ざらり、ざらり──
見えない舌は、法子の意識を殺ぎ落とすように女芯を攻める。膣の入口から中へ差し入れて出し入れし、クリトリスを器用に剥き上げて転がし、会陰を通ってアヌスまでも──。
「いやぁぁぁ、だめぇぇ……あ、あ、あ!」
今、自分は尋常じゃない状態なのだ。この上にクンニなどされたら──。
既に法子の女芯は愛液と唾液でどろどろになっていた。
膣口はくぱぁ、と開き、ピンク色のクリトリスは天を向いて屹立し──奥から湧き出る蜜は白濁し始めている。
「い、いやぁ!! もうダメ、ダメ、だめぇぇぇ……」
舌は次第にクリトリスに焦点を合わせて攻め始めていた。
言うまでもなく、ここに強い女性などいない。屹立しているクリトリスを転がし、擦り、擦り付け、吸い、噛み──法子の身体はその度に跳ね上がり、喉からは絹を切り裂くような叫びが洩れた。
「ひ、ひい、ひいっ、ひいいいっ!! き……いいいっ!!」
そして、法子の陥落はあっさりと訪れてしまった。
「あ……あ! ……きぃ、ぃいいやあああああーーーーーーっっっ!!!!!」
|
がくがく、がくがく、と法子の身体は壊れた機械のように痙攣する。 驚愕したように目を大きく見開き、ケモノのような叫びを迸しらせていた。 深い絶望と、羞恥と、嫌悪を感じながら──法子の表情は、段々と喜悦に歪んでいく。 「ふうぅ、ふう、ふううぅ、ふううぅ、ふううう……」 唇をすぼめ、目を瞑り、頤を見せるように首を反らせ──それはもう、女というよりはケモノの雌の貌だった。 だが── 『まだまだだ』 「──え? ……ひぃ!!」 今度ははっきりした声を聞いた、と思った瞬間、猛烈な舌攻めが再開された。 指のようなもので秘裂を広げられ、クリトリスの包皮をめくられ、そこに無茶苦茶に舌が暴れ回る。 「ひ・ひぃ、ひいいぃ──!!!」 口をぱくぱくとさせながら、法子はあっさりと絶頂した。 先刻の絶頂がまだ終わらぬうちの刺激と絶頂。いわゆる「イキっぱなし」の責め苦が法子を襲っていく。 「あ、あぐ、あ、あ、あ……」 何度も── 「ぎ、ぎひぃぃいいいーーーっ!!!!」 何度も── 「……ぎ……ぃ……あ……あ……ああぁ……」 法子が完全に失神してしまうまで、攻めは続いた。 いくら身体が跳ね回っても、見えない舌と指は決して離れる事がなく、またどんなに法子が泣き叫んでも攻めを容赦しようともしなかった。 「…………!! …………!!! ………………っ!!!!」 法子の身体と精神はとうとう限界を迎え、彼女は棒切れのように畳に倒れ込む。 ……それから先は、何も覚えていない。 |
 |
◇
法子が失神から覚めたのは、それから1時間ほどもした後だった。
隣のリビングに射し込む光が、大分傾いている。何の変哲もない、晴れた平日の午後。
 |
畳に寝転がった状態で、法子はただぼぉっとそんな情景を眺めている。 少しずつ、少しずつ先刻の記憶が蘇ってきて、羞恥と絶望が法子の脳裏をぐるぐると回っていた。 「う……」 涙が、ひとすじ法子の頬を伝った。 汚されてしまった。夫ではない男に。 自慰などという痴態を晒し、しかもイッてしまった。 そして「何か」に舌で攻められて、イカされてしまった。何度も何度も。 何より彼女自身を追い詰めていたのは──自分が、感じてしまったという事だ。 今まで味わった事もない快楽に喜悦の表情を浮かべ、ケモノのように愉悦の叫びをあげ、絶頂の度に身体は震えて泣き咽んだという事。 そして、自分の身体があの快感を感じ――それを、覚えてしまったという事。 もし再びあのような衝動が襲ってきたら──そして、「何か」のあの舌の攻めを受けてしまったら──もう、抵抗すらできる自信はない。 絶望感に、目の前が真っ暗になる。消え入りたい気分だった。 「うっ、うぅ……」 |
夫は、夜の生活こそ淡白ではあったが、素晴らしい男なのだ。包容力があり、穏やかで、家族を見る目は慈愛に満ちていた。
それを自分は、欲望と快楽に負けて、裏切ってしまった──。
涙が、止まらなかった。
「あなた……ごめんなさい……」
法子は、畳の上に身を投げ出したまま、泣き続ける。
しかし、彼女を襲った災厄は、未だに終わっていなかったのだ。
◇
|
ことん、という物音に、法子はびくりと振り返った。 先程の慟哭がまだ収まっていない法子の貌は、悲哀から恐怖へと変わり、歪んでいく。 「あ……」 そこには、ピンク色をしたバイブレーターが、宙に浮いていた。 「ひっ……」 恐怖に引きつりながら、法子は必死に後ずさる。 『動くな』 低い声が命じた途端、法子の身体は金縛りのように動かなくなった。 「!?」 身体が、全く動かない。困惑にパニックを起こしそうになっている間に、バイブレーターは目の前に迫って来ていた。 「や……めて、もう、やめてぇ……」 がくがくと震えながら、見えない何者かに向かって哀願する。 『ふん。さっきはあれほど感じてヨガっていたメス犬が、何を今更貞淑ぶっている』 声が応えた。耳元でいきなり、声が囁いたのだ。法子はびくりと身を震わせて逃げようとしたが、やはり身体は動いてくれなかった。 「だ……れ、誰なの!?」 必死で視線を巡らし、声の主を探す。だが、どこにも姿は見えなかった。 『お前の真の主だ。お前はこれから私の性奴として生きるのだ』 「そんな……!! 私には、れっきとした主人がいます! あなたなんかの所有物ではありません!!」 法子は言いながら、必死で男の姿を探し続ける。 しかしすぐ側で声はするのに、そこには誰もいないのだ。ただ、バイブレーターが宙に浮いて、不気味な威圧感を放っている。 『そうかな? 先程のお前の痴態……』 「──やめて!!」 『くっくっく、怖い怖い』 |
 |
声には不遜なまでの自信と、余裕が感じられた。次第に法子の頭の中に、焦燥と絶望が沸き上ってくる。
『くっくっく、おまえのその虚勢、どこまで持つのか見物だな』
「わ……私は、あなたなんかに屈しません!!」
宙に向かって、叫ぶ。応えたのは、くっくっくっという嘲笑だった。
『夫への操、か。立派なものだな』
「何を……」
『ではこれは、何なのだ?』
突然、宙に浮いていたバイブレーターがブン、と動き始めた。カッと、法子の顔に朱が射す。
「!! ……それは……」
それは法子が先日、自らを慰めるという痴態を演じた時の物だった。
自分の一番の恥部を晒され、彼女のプライドはズタズタになっていく。
『こんな物で自分を慰めていて、何が貞淑だ!! はっはっは!!』
「そん……な、嘘……です」
法子の応えに、最早今までの力はない。
 |
『どぉれ、それではお前が本当に貞淑な妻なのか、試してやる。──脚を開け』 途端に、法子の両脚ががばっと開かれる。 「い、嫌ぁぁっ!!」 身をよじって恥辱から逃れようとするが、身体は少しも法子の言う事を聞こうとしない。 どうして──!? 神経が焼き切れそうなほどに混乱した中、法子は必死に考える──だが、追い詰められた心理状態でそんな疑問に答えられるはずもなく、そうこうしているうちに何かの気配が近付いてしまっていた。 『本当に貞淑なら、私なぞにイカされたりなどしないだろう……?』 バイブレーターがふわりと動き、法子の中心の前に止まる。 「や、やめてぇぇ!!」 法子は弾かれたように取り乱し、必死になって見えない束縛から逃れようとした。 ──が、やはりぴくりとも動かない。 彼女の拒絶を無視し、バイブレーターはどんどん迫ってくる。 『そうだな、これから30分、イカないでいられたら、私もお前が貞淑な妻だったと認めてやろう』 「そ、そんな……」 全く身体が動かない──法子はただ、カタカタと震えながらバイブレーターを見つめる事しかできなかった。 その貌に浮かぶのは恐怖、焦燥、絶望、危機感、喪失感、憎しみ、嫌悪、疼き、罪悪感──それらがめまぐるしく入れ替わり、そして混じり合っていた。 逃げられない。助けも来ない。 自分は嬲られているのだと、遊ばれているのだと、法子は絶望的な思いの中で悟っていた。 「やめて、助けて……」 『たまらないぞ、その表情……』 「あぁ、あぁぁぁ……」 つぷり。 |
先端と入口が触れ合った。
『くっくっく……そら、入っていくぞ……』
「嫌ぁ、いやぁぁぁ……」
ずぷ、ずぷずぷずぷ……
弱々しくもがこうとする法子の様子を楽しむように、
バイブレーターはゆっくり、ゆっくりと彼女の女芯へとのめり込んでいった。
亡霊の住む家 14 に続く